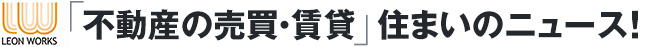パート主婦の収入と税金・社会保険の複雑な関係を紐解く
「103万円の壁」という言葉は、パートで働く主婦の方々にとって、もはや聞き慣れた言葉でしょう。この壁を超えると、所得税がかかり始め、夫の配偶者控除も受けられなくなるため、世帯全体の収入が減ってしまうという問題があります。しかし、103万円の壁を超えた後も、様々な「壁」が待ち受けています。

本コラムでは、103万円の壁を超えた後の状況、つまり「次の壁」について、税金や社会保険の制度を踏まえながら、より深く掘り下げていきます。パート主婦の方々が、自身の収入と税金・社会保険の関係を正しく理解し、より良い働き方を選択できるよう、具体的な事例を交えながら解説します。
103万円の壁を超えると何が変わるのか?
103万円の壁を超えると、主に以下の2つの大きな変化が起こります。
- 所得税の発生: 103万円を超える収入に対して、所得税が課税されるようになります。
- 配偶者控除の喪失: 夫が受けられる配偶者控除がなくなります。
これらの変化は、世帯全体の収入に大きな影響を与えます。所得税の金額は、収入額や扶養家族の数などによって異なりますが、年間数万円から数十万円の追加負担となるケースも少なくありません。また、配偶者控除がなくなると、夫の所得税額が増加し、世帯全体の可処分所得が減少します。

103万円の壁の次の壁①:106万円の壁
103万円の壁を超えると、すぐに106万円の壁が立ちはだかります。この壁は、社会保険の加入が義務付けられる可能性があるという点で重要です。
- パート先の規定による: 106万円を超えた場合、必ずしも社会保険に加入しなければならないわけではありません。パート先の規定によって異なります。
- 社会保険料の負担: 社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料を支払う必要があります。
- 手取り額の減少: 社会保険料の負担が増えるため、手取り額は大きく減少します。
103万円の壁の次の壁②:130万円の壁
130万円の壁は、社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を全額負担しなければならないという点で、大きな壁となります。
- 社会保険の扶養から外れる: 130万円を超えると、原則として夫の社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
- 社会保険料の負担増: 国民健康保険料や国民年金保険料は、健康保険や厚生年金保険料に比べて負担が重くなる場合があります。
- 年金受給額への影響: 国民年金は、厚生年金に比べて将来受け取れる年金金額が少なくなります。
103万円の壁の次の壁③:150万円の壁
2018年の税制改正により、配偶者特別控除の満額を受けられる年収が103万円から150万円に引き上げられました。しかし、150万円を超えると、配偶者特別控除の金額が段階的に減額されていきます。
- 配偶者特別控除の減額: 150万円を超えると、夫が受けられる配偶者特別控除の金額が減額されていきます。
- 夫の所得税額の増加: 配偶者特別控除が減額されると、夫の所得税額が増加します。
収入の壁を超えた場合の対策
収入の壁を超えた場合、どのように対策すれば良いのでしょうか。
- 税理士や社会保険労務士に相談する: 税金や社会保険の手続きは複雑です。専門家に相談することで、最適な方法を見つけることができます。
- パートの働き方を工夫する: 週の勤務時間や勤務日数を調整することで、収入を調整することも可能です。
- 副業を検討する: パート収入に加えて、副業で収入を得ることも一つの選択肢です。
- 年金制度について学ぶ: 国民年金や厚生年金の違い、将来の年金受給額などを理解しておくことが大切です。
まとめ
103万円の壁を超えた後も、様々な「壁」が待ち受けています。パート主婦の方々は、これらの壁を意識し、自身の収入と税金・社会保険の関係を正しく理解することが重要です。
年収103万円の壁(所得税)については以下リンクコラムへ記載しております。
年収150万円の壁(配偶者特別控除)については以下リンクコラムへ記載しております。