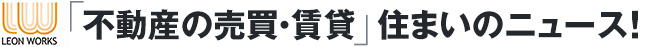土地にはいろいろな種類がありますが、相続した土地が市街化調整区域だった場合、一般的な土地の評価とは異なります。
もし相続した土地が市街化調整区域だったら、どうするのが良いのでしょうか。
そこでこちらの記事では、市街化調整区域とはなにか、路線価や相続税評価はどうするかを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む
路線価に影響する市街化調整区域とは何か
「市街化調整区域」とは市街化を抑制するために定められたエリアです。
都道府県や市町村などの自治体が都市計画法に沿って決めています。
指定された土地は用途が制限され、原則として勝手に住宅など建設はできません。
もしエリア内に建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可が必要です。
調整区域は路線価が付されていないのが一般的で、その価値は倍率方式で決まります。
倍率方式とは、そのエリアの固定資産税評価額に宅地・山林・田・畑などの地目に応じた倍率をかけて評価する方法です。
属性に対する倍率は「評価倍率」といい国税庁が定めています。
▼この記事も読まれています
不動産相続を控えている人必見!空き家の解体費用や補助金制度とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む
路線価のない市街化調整区域内にある土地の相続税評価とは
相続のときに必要な評価額は「路線価方式」または「倍率方式」で決まります。
しかし、調整区域は路線価がない場合が多く、倍率方式で算出するのが一般的です。
倍率方式は固定資産税評価額に応じた倍率をかけて計算しますが、雑種地のような倍率が定められていない土地の種類もあります。
このような場合は対象の土地と状況が類似する地目をもとに計算しましょう。
ただし、調整区域は建物への制限などがあるため、近傍の宅地に比準した額から50%ダウンします。
減価率はしんしゃく割合といわれ、相続税評価額は「類似の固定資産税評価額×(1-しんしゃく割合)×評価倍率」で計算します。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議とは?進め方と多発するトラブルの解決策もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む
相続した路線価のない市街化調整区域はどうするのか
市街化調整区域の土地は、建物を建てるのにも制限があり活用しにくいのが問題です。
相続した土地が調整区域の場合、活用できなくても管理義務が発生し、土地の管理にかかる負担をしなくてはなりません。
相続放棄をしても管理責任は残るため、どうするかは慎重に検討したほうが良いでしょう。
売却する方法もありますが、土地の特性をきちんと買い手に伝える必要があります。
先祖伝来の土地などで売却できない場合は、賃借権や地上権を設定して土地を貸す方法があります。
土地が遠隔地にある場合や忙しくて管理する時間が作れない場合は、信託会社や信託銀行に所有権を移し、土地信託をするのも可能です。
土地の活用は信託会社がおこない、収益から一定の金額を配当として受け取れます。
▼この記事も読まれています
空き家の相続放棄とはなにか?管理責任や手放すための方法
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む

まとめ
市街化調整区域は市街化を抑制されたエリアで、建物を新築するときには都道府県知事の許可が必要です。
制限があるエリアになり、活用が難しくなりますが、相続をすると管理義務が発生します。
管理が難しい場合は、売却や土地信託を検討し自己負担を軽減できるようにしましょう。
関西の分譲マンションのことなら株式会社レオンワークスにお任せください。
関西圏で投資用、居住用のマンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
関西の売買戸建て一覧へ進む